お子さんの就学先を考えるとき、避けて通れないのが「就学相談」です。
「支援学校がいいのか、支援学級なのか、それとも通常学級なのか…」
と悩む保護者は少なくありません。
就学相談は、教育委員会や専門機関が中心となり、子どもの発達や学習・生活の様子をもとに、最適な学びの場を一緒に考えるプロセスです。
とはいえ、初めて経験する保護者にとっては不安も多いもの。
「どんな流れで進むの?」「準備は必要?」「結果はどんなふうに決まるの?」など、疑問が尽きないのではないでしょうか。
この記事では、就学相談の基本から実際の流れ、確認されるポイント、保護者ができる準備までを丁寧に解説していきます。
就学相談とは
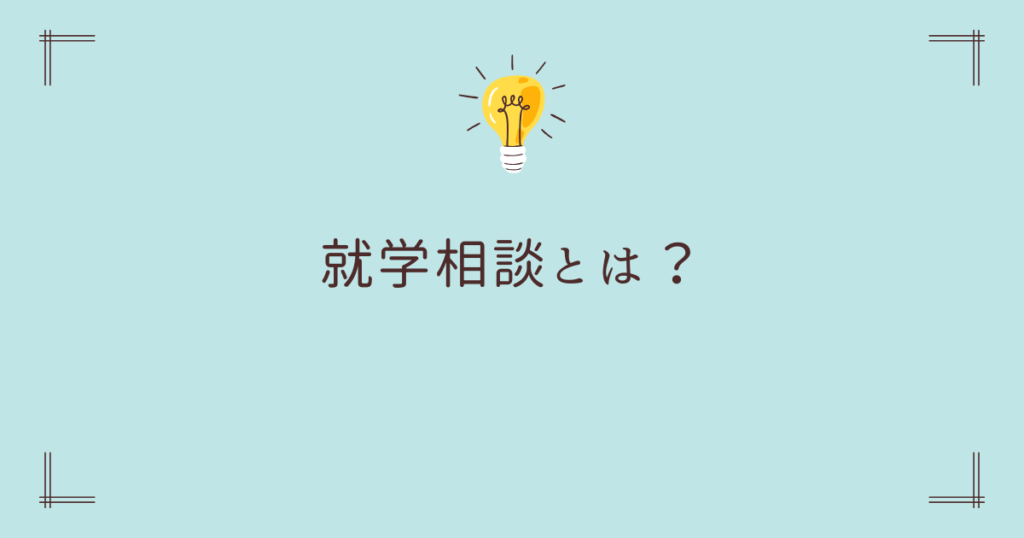
就学相談とは、就学を控えた子どもの学習や生活の様子を確認し、どのような教育環境が適しているかを教育委員会や学校と一緒に考える場です。
通常学級、特別支援学級(情緒・知的など)、特別支援学校、それぞれの特徴をふまえて「子どもにとって安心して成長できる場所」を探します。
特別支援学校と特別支援学級の違いはこちらの記事をご覧ください。
保護者だけで判断するのは難しいため、専門的な視点からの助言を受けながら方向性を考えるのが就学相談の役割です。

「就学相談=学校側が一方的に決めるもの」ではなく「保護者と一緒に考えるプロセス」と理解すると安心です。
就学相談の流れ
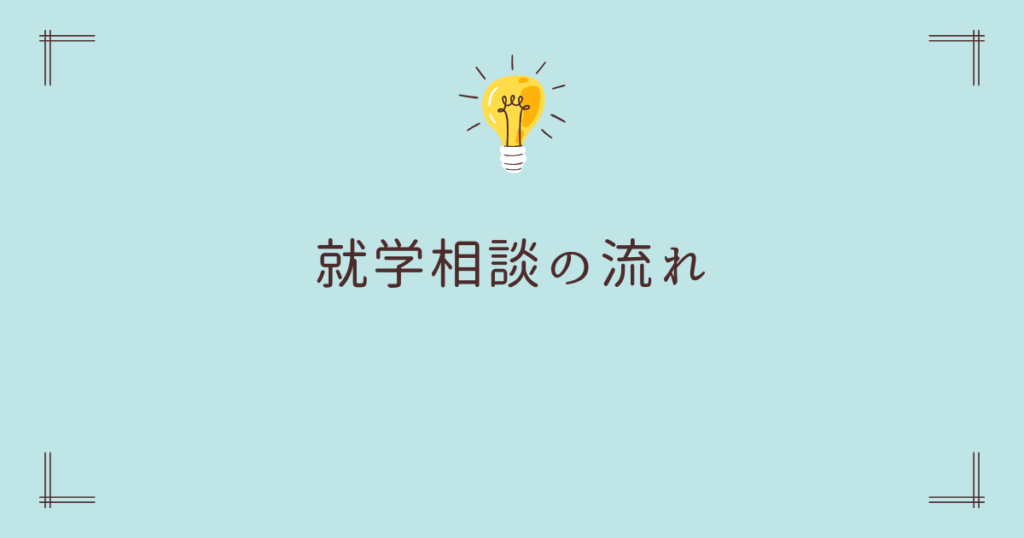
就学相談は自治体によって手順やスケジュールに多少の違いはありますが、大まかな流れは共通しています。
①教育委員会への申し込み
②面談
③専門委員による観察
④保育園や幼稚園からの意見書
⑤判定会議
⑥保護者への説明・就学先の決定
教育委員会への申し込み
まずは教育委員会へ「就学相談を受けたい」と連絡します。
市区町村によっては園や学校から案内が届くこともあります。

就学の1年前(年長になった年度)の4月から9月ごろに申し込みます。
面談
保護者と子どもが一緒に訪問し、これまでの発達や生活の様子について面談します。
保護者の言葉はとても重要な情報源になります。
お子さんの日々の様子を細かく伝えましょう。
③ 専門委員による観察
心理士などの専門員がなどが子どもの生活の場(保育園等)を訪問し、行動観察を行います。
保育園や幼稚園からの意見書
日常の集団生活での様子をふまえ、園からの意見書が教育委員会に提出されます。
家庭とは違う一面を知る大切な材料になります。
判定会議
教育委員会の専門職や学校関係者が集まり、子どもに合う就学先について話し合います。
ここでの判断は「どこが合うかを考える」ためのものであり、子どもの可能性を狭めるものではありません。
保護者への説明・就学先の決定
最終的に教育委員会から保護者へ結果が伝えられます。
その後、保護者と学校での打ち合わせが始まります。
最終的な就学先の決定は12月~1月ごろとなる地域が多いです。

いきなり“ここに決まりました”と告げられるのではなく、保護者と相談しながら進んでいきます。就学先の決定権はお子様本人と保護者にあります。
就学相談で確認されるポイント
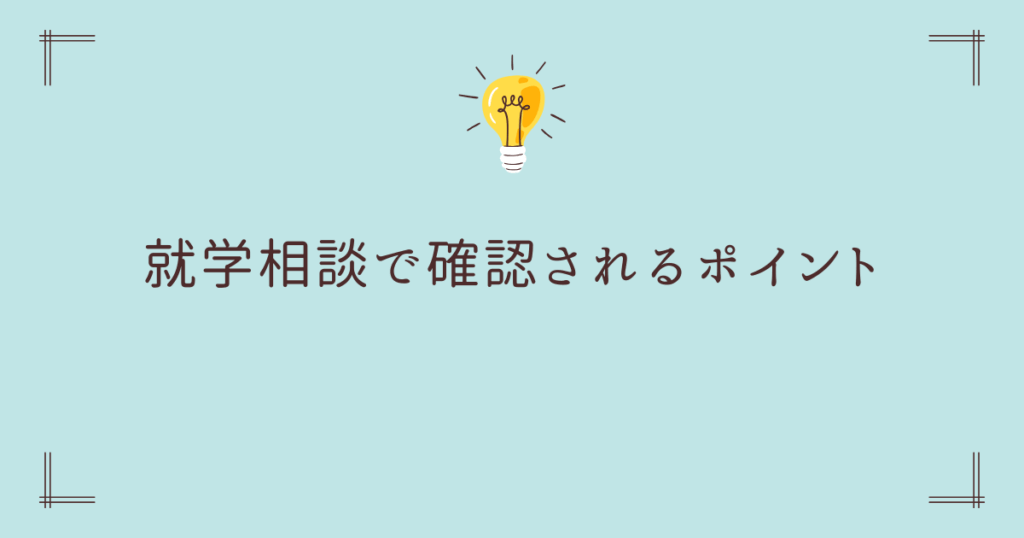
就学相談で確認されるポイントをまとめました。
- 読む力
- 書く力
- 数や計算の理解
- 集団での行動
- 生活スキル
読む力
絵本や文字カードを使って、名前を指さしたり、簡単な指示に従えたりするかを観察します。
ここで大切なのは「完璧に読めるか」ではなく、文字や指示に反応できるかどうかです。
書く力
鉛筆やクレヨンで線をなぞったり、簡単な文字を書く遊びを通して、書くことへの興味や集中力を確認します。
遊びの中で自然にできるかを見ることで、子どもの学習への適応力がわかります。
数や計算の理解
おもちゃや数カードを使って「いくつあるか」「分ける・合わせる」といった操作を通し、数の理解や操作の感覚をチェックします。
数字がまだ読めなくても、手を使った操作で理解の様子を確認できるのがポイントです。
集団での行動
先生の指示に従えるか、順番を守れるか、友達とのやり取りや集団活動での適応力を観察します。
これは、支援学級や通常学級での学び方を考える際に、とても参考になります。
生活スキル
着替え、食事、トイレなどの日常生活での自立度も確認されます。
学校生活では、この基礎があることで安心して学びを進められるからです。

就学相談はテストの場ではありません。遊びや日常のやり取りを通して、子どもに合った学びの環境を一緒に探す時間です♪
参考:文部科学省「就学相談・就学先決定の在り方について」
就学相談に向けて保護者が準備しておくとよいこと
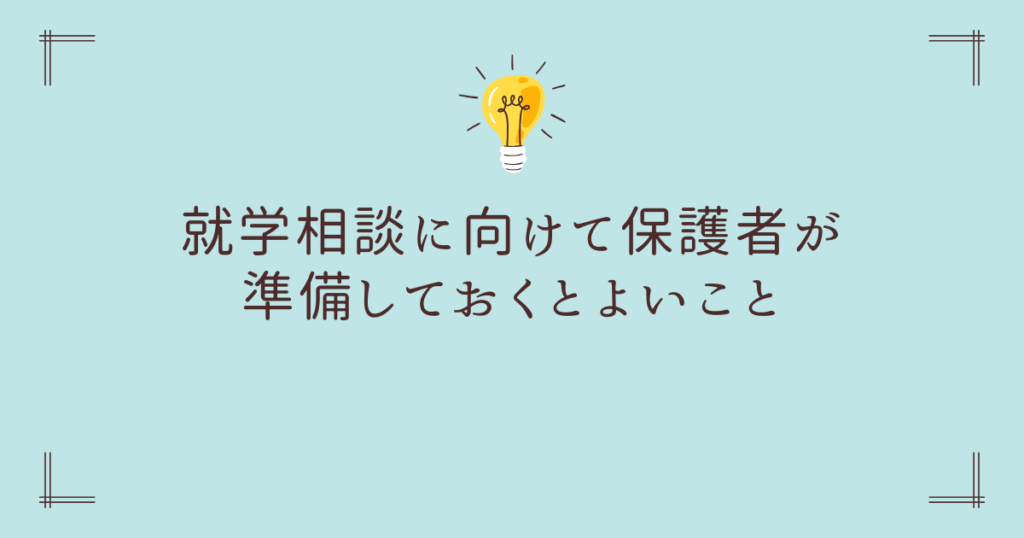
学相談に向けて、保護者がしておくと安心な準備があります。
- 家での様子を具体的にメモしておく
- 苦手なことだけでなく得意なことも伝える
- 「小学校生活で大事にしたいこと」を整理しておく(学習?生活力?交流?)
- 園の先生とも子どもの様子を共有し、意見をもらっておく

“困っていること”と同じくらい、“得意なこと”を伝えることが、子どもの強みを生かすヒントになります。
就学相談を通して得られるもの
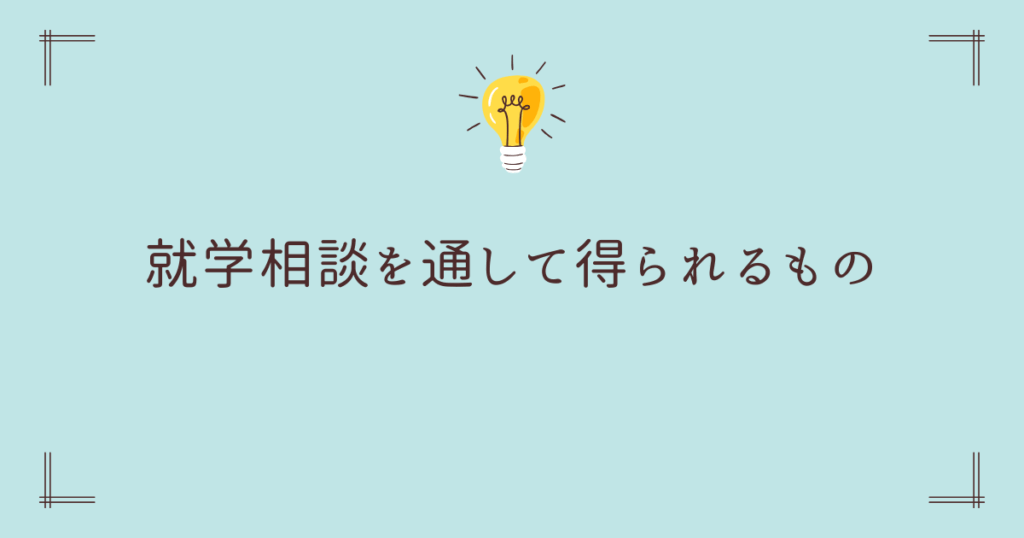
就学相談は不安も大きいですが、実は保護者にとって学びの機会でもあります。
- 子どもの得意や苦手を整理できる
- 専門職から客観的な意見をもらえる
- 将来を見据えて、どの力を優先的に育てたいか考えるきっかけになる
相談を通して、保護者自身が「子どもの成長をどう支えたいか」を見直す機会にもつながります。
まとめ:就学相談の流れをわかりやすく解説|支援学校・支援学級を考える保護者へ
就学相談は「子どもの未来を縛る場」ではなく、「今に合った学びの環境を探すためのプロセス」です。
不安を抱えながら臨む保護者は多いですが、相談の場を通して子どもの強みや課題が整理され、安心してスタートを切る準備になります。
大切なのは「子どもに合う環境を一緒に探す」姿勢です。
相談を重ねながら、子どもが安心して学び、成長できる就学先を選んでいきましょう。

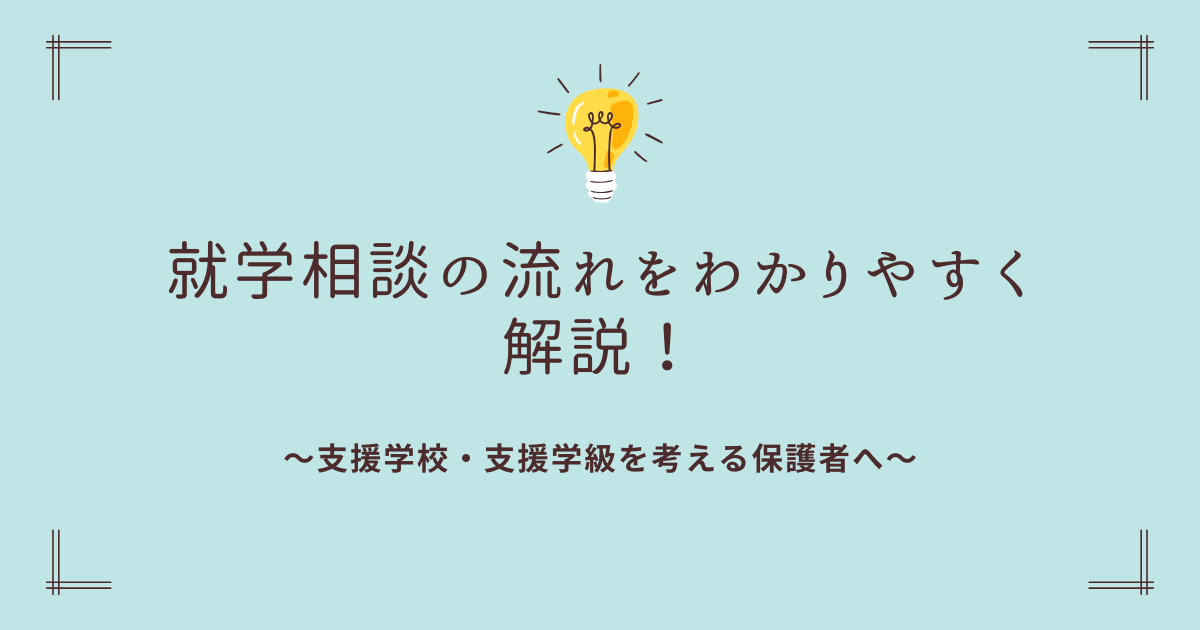
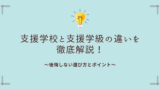

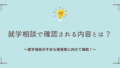
コメント