「うちの子、支援学校と支援学級どちらが合うんだろう」
子どもが発達支援や学習支援を必要とする場合、保護者にとって「支援学校と支援学級のどちらを選ぶか」は大きな悩みのひとつです。
どちらの選択も、子どもの学びや社会性、将来に大きく影響します。
実際に検索している保護者の多くは、違いやメリット・デメリットを比較したいと考えています。
しかし、情報が分散していて理解しづらいことも多いのが現実です。
この記事では、「支援学校」と「支援学級」の違いを分かりやすく整理し、それぞれの特徴・メリット・デメリット・選ぶときのポイントを具体的に解説します。
この記事を読むことで、子どもに合った教育環境を見つける手助けになります。
支援学校とは?
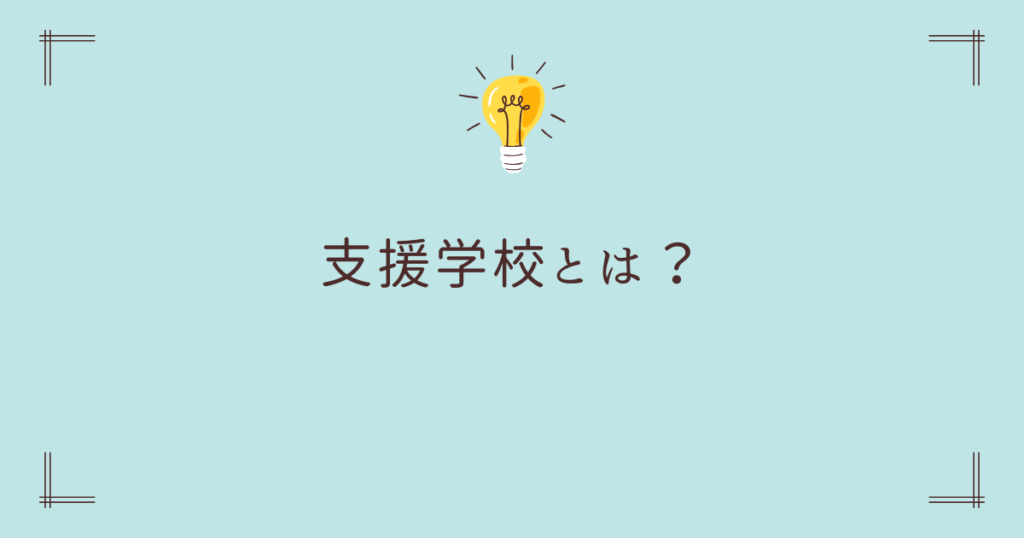
支援学校は、障がいのある子どもが個々の特性に合わせた教育を受けられる学校です。
知的障がいや肢体不自由、情緒障がいなど、通常学級では学びにくい子どもが通います。
授業は個別カリキュラムを中心に行われ、学習だけでなく生活スキルや社会性も同時に育てられます。
クラスは少人数制なので、先生が一人ひとりに目を配れる環境です。

習だけでなく、生活スキルもしっかり身につけられる!
支援学校のメリット
支援学校のメリットはこちら。
- 同じ特性の子どもたちと一緒に学べる
- 専門的な支援を手厚く受けられる
- 生活スキルの自立に向けたサポートが受けられる
- 将来を見据えた就労の訓練ができる
支援学校のデメリット
一方で、支援学校にはこんなデメリットがあります。
- 地域の通常学級との交流は少なめ
- 特別支援学校の高等部を卒業しても「高卒」資格が得られない
- 進学先が限定される(学習が遅れるため)
支援学校は、本人の苦手なことに焦点を当てたカリキュラムを組んでいるため、学習の進度が通常の学校よりも遅れてしまいます。
そのため、途中で進路を変更したくなった場合に難しいこともあります。
特別支援学級とは?
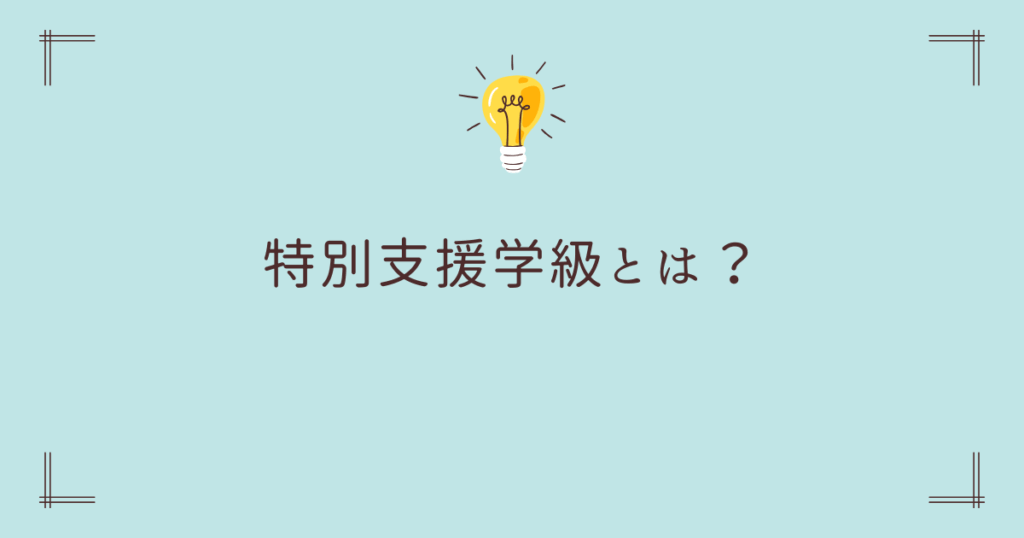
特別支援学級は、通常の小中学校に設置されています。
学習や生活に支援が必要な子どもが対象で、通常学級のカリキュラムを調整しながら学べます。
授業は個別指導中心ですが、通常学級との交流も多く、学校行事や休み時間に地域の子どもと関わることも可能です。
支援学級には、大きく分けて情緒クラスと知的クラスがあります。
情緒クラスは、集団行動や感情のコントロールに支援が必要な子どもが中心で、学習内容も生活面も柔軟に調整されます。
知的クラスは、学習面に支援が必要な子どもが中心で、基本的な学力や生活習慣を段階的に身につけられるように指導されます。

知的クラスでは、子どもの理解度に合わせて学習を進めます。そのため、通常学級との学習進度の差が出やすいです。

情緒クラスの学習の進度は、通常学級とほぼ変わらないことが多いよ。

将来的に通常学級に戻ることを考えているなら、学習進度に差がでないよう学校側と話し合いましょう。
特別支援学級のメリット
特別支援学級のメリットはこちら。
- 通常学級との交流ができる
- 地域の子どもと一緒に学べる
- 学習面、生活面の個別的なサポートが受けられる
- 進路の選択肢が広がる
特別支援学級のデメリット
特別支援学級のデメリットはこちら。
- 支援内容や授業の進め方は学校ごとに差がある
- 学習進度が遅くなったり、内容に偏りが出てしまうケースもある
- 専門性をもった教員が少ない
支援学校と支援学級の違い
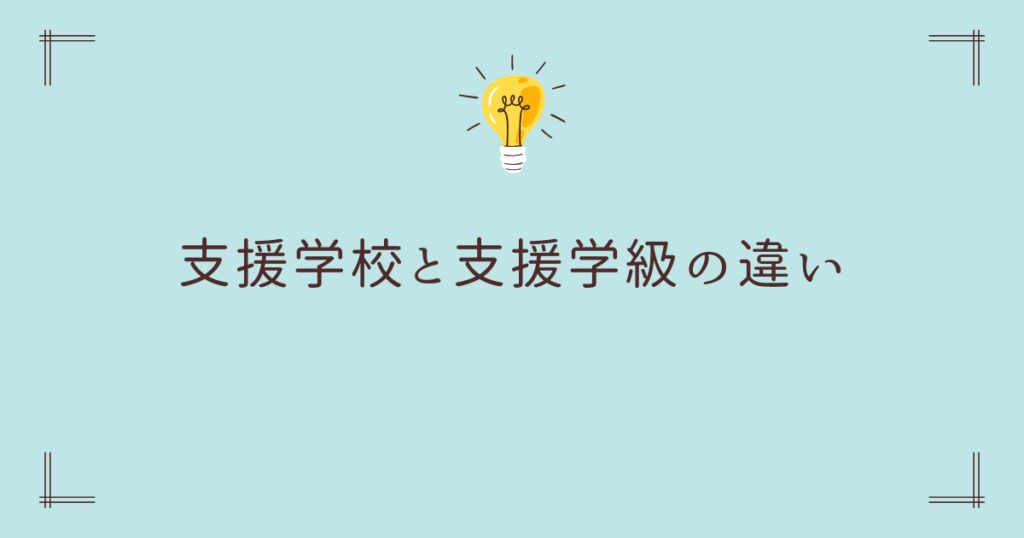
支援学校と支援学級の違いを表にまとめました。
| 項目 | 支援学校 | 支援学級 |
|---|---|---|
| 対象 | 障害の程度に応じた児童 | 通常学級で学ぶのが難しい児童 |
| 教育内容 | 個別カリキュラム、生活単元学習 | 通常学級と調整した特別支援 |
| クラス分類 | 障害別(知的・肢体不自由・情緒など) | 情緒クラス・知的クラス |
| 交流 | 同じ特性の子中心 | 通常学級との交流あり |
| 定員 | 少人数制 | 学校により異なる |
| 施設 | 専門設備あり | 通常学校の設備を利用 |

学習面や地域の子どもとの交流の面で大きな差が出ます。

お子さんの特性や将来の姿を見据えて選ぶのがいちばん!
支援学校・特別支援学級を選ぶときのポイント
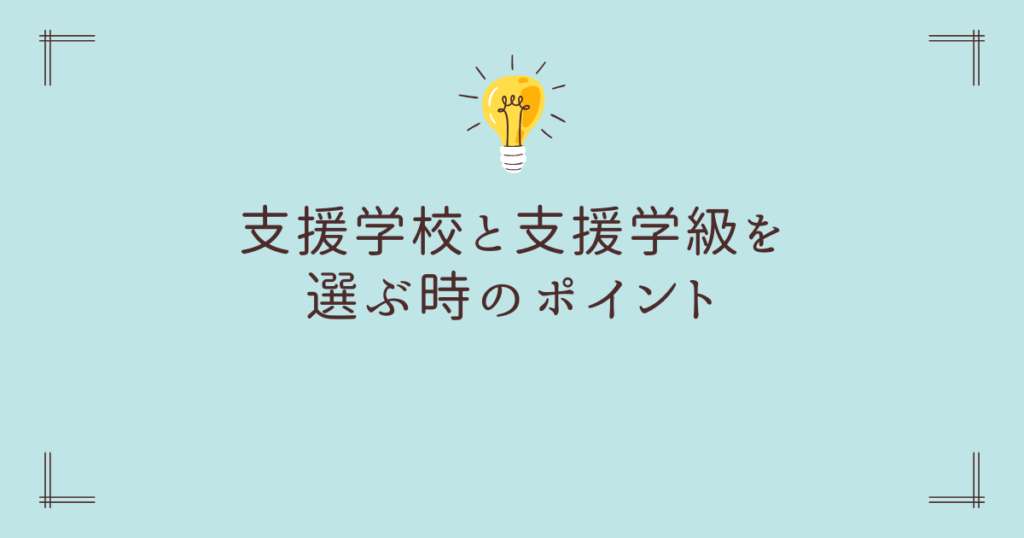
支援学校、支援学級を選ぶ時のポイントはこちら。
- 子どもの特性を理解する
- 家庭の希望、生活スタイルを考慮
- 学校の環境や教育内容を理解する
- 将来の進路・目標を見据える
子どもの特性を理解する
学習面、生活面、社会性の3つの視点で観察します。
学習面
読む・書く・計算の理解度や集中力、理解スピードを確認します。
理解が遅めでサポートが必要なら、個別指導や少人数制の環境(支援学校や知的クラス)が向いている可能性があります。
理解が比較的早ければ、支援学級の情緒クラスや通常学級との交流も視野に入れられます。

学習の理解度に合わせて環境を選ぶことが大切です
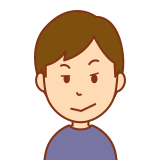
うちの子は計算は得意だけど、集中力が続かないので少人数で見てもらった方が安心ですね
生活面
身の回りのこと(着替え、手洗い、食事など)がどの程度自立しているかを確認します。
自立度が低い場合は生活スキルを重点的に育てられる支援学校が適していることが多いです。
ある程度自立していれば、支援学級で通常学級の生活リズムに合わせて成長できる場合があります。

三大自立といわれる「トイレの自立」「食事の自立」「着替えの自立」は特に大切です。
社会性
友達との関わり方や集団行動の得意・不得意を観察します。
友達と一緒に行動するのが難しい場合は少人数制で安心できる環境(支援学校や情緒クラス)が向きます。
集団行動が得意であれば、支援学級で通常学級との交流を通して社会性を伸ばす選択も可能です。
家庭の希望、生活スタイルを考慮
特別支援学校は地域の学校と違い、自宅の近くに無い場合も多く、通学バスを使っての通学になる場合が多いです。
そのため、バス停までの送迎をどうするのか、お子さん自身が長時間バスに乗っていられるかなどを考慮する必要があります。

家庭でどれだけサポートできるかも考える必要があります
学校の環境・教育内容を確認する
両者では学校の環境や教育の内容も大きく違うため、よく確認しましょう。
- 支援学校か支援学級かで学習内容や授業形式が異なる
- 支援学級の場合は、情緒クラス・知的クラスの違いもチェック
- 教室の雰囲気や先生のサポート体制も重要

クラスの人数や先生の配置によって、子どもに合うかどうかが大きく変わります

授業の進め方や支援方法を見学で確認することが大事ですね
将来の進路・目標を見据える
将来的な就学や就職、社会参加を見据え、子どもが学習や生活の基礎をどの環境で身につけるかを考えることが大切です。
支援学校では専門的な支援体制が整っており、生活スキルや社会性をじっくり育てることができます。
一方で支援学級では、通常学級との交流を通して友達との関わりや集団での適応力を伸ばすことができ、社会性を育む場として非常に有効です。

未来を見据えるって大変ですよね。まずは、大きくでいいので、一般就労を目指すのかどうかを考えてみましょう。迷った時はその子をよく見てくれる専門家に相談するのもいいですね。
支援学校と特別支援学級の違いに関するよくある質問
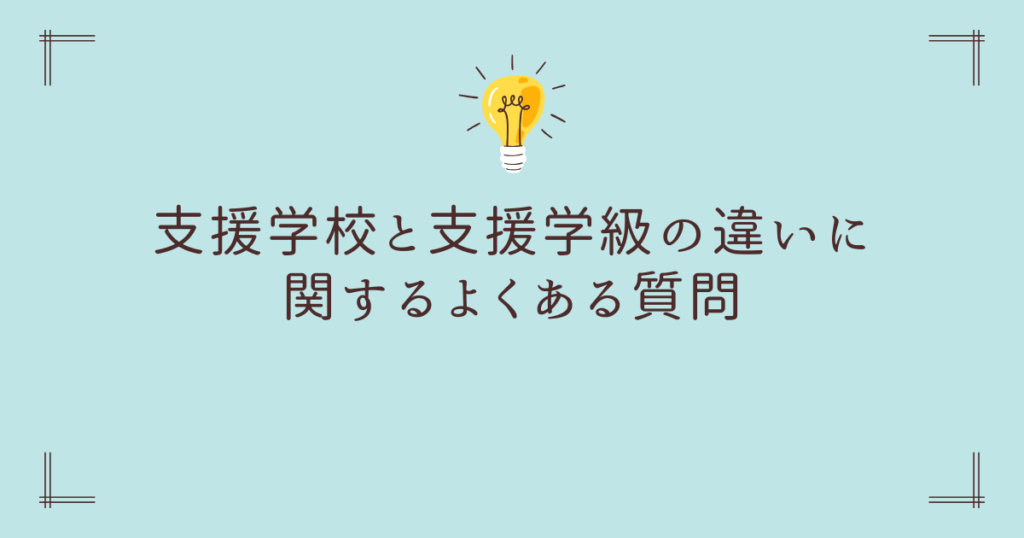
次に、支援学校と特別支援学級の違いに関するよくある質問にお答えします。
支援学級から支援学校に変更できますか?
可能です。子どもの成長や特性に応じて、市町村の教育委員会に相談すると手続きできます。
通級指導教室とは何ですか?
通常学級に通いながら、特別な学習や支援を週1〜2回受けられます。
学習や生活面のサポートに役立ちます。

情緒面に苦手あるお子さんは、ソーシャルスキルトレーニングを実施したり、授業の内容を抜き出して個別で教えてくれる学校もあります♪
まとめ|支援学校と支援学級の違いを徹底解説|後悔しない選び方とポイント
支援学校と支援学級には、それぞれメリット・デメリットがあります。
子どもに合った環境を選ぶことが最優先で、どちらが良い悪いではありません。
見学や教育相談を活用し、家庭の希望や子どもの特性を確認することで、後悔のない選択が可能です。

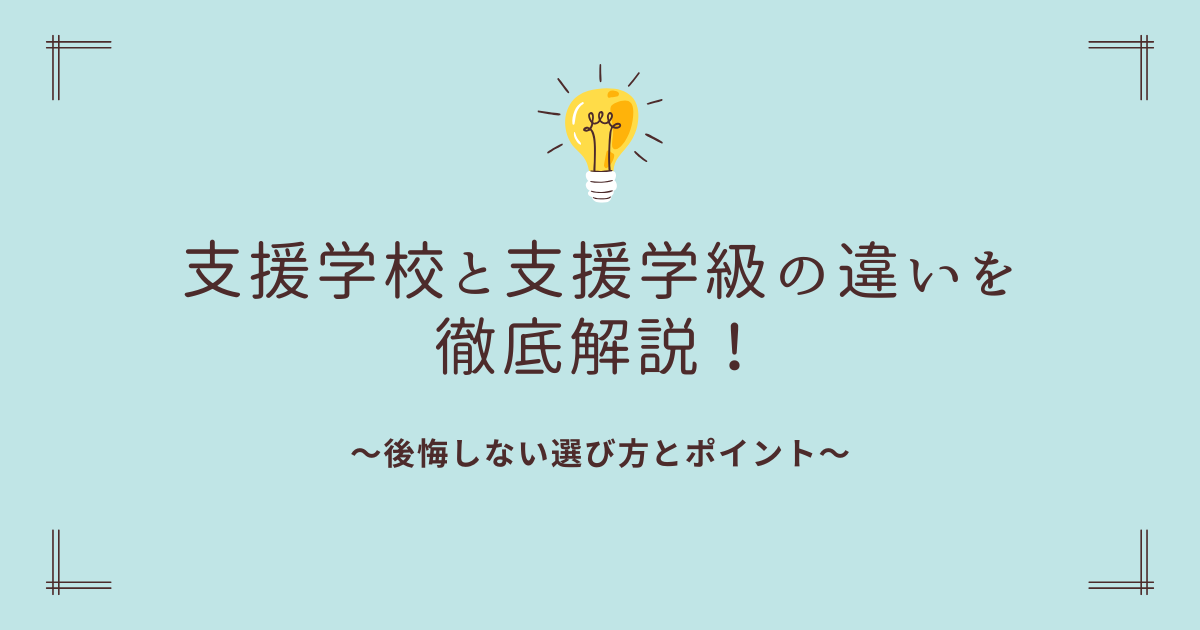
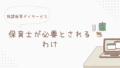
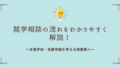
コメント